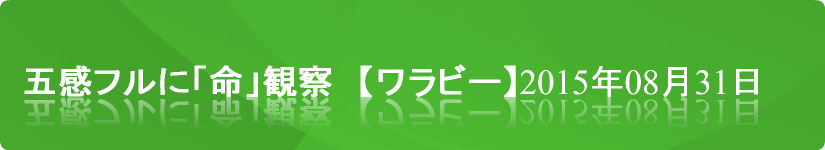2015年08月31日(日) ワラビー
子ども調査隊8人 地球環境考える
久米島特有の自然を体感
子(こ)どもたちが環境(かんきょう)について考(かんが)える「沖縄(おきなわ)こども環境調査隊(かんきょうちょうさたい)2015」の隊員(たいいん)8人(にん)が7月(がつ)28日(にち)から31日(にち)まで久米島(くめじま)を視察(しさつ)しました。
森(もり)、湿地(しっち)、川(かわ)、海(うみ)に出向(でむ)き、ふだん意識(いしき)することのない小(ちい)さな生(い)き物(もの)や島(しま)の固有種(こゆうしゅ)について理解(りかい)を深(ふか)めました。
シュノーケリングで赤土(あかつち)の流出(りゅうしゅつ)によるサンゴへの悪影響(あくえいきょう)を視察(しさつ)し、夜(よる)の洞窟探検(どうくつたんけん)で食物連鎖(しょくもつれんさ)について学習(がくしゅう)しました。
子(こ)どもたちは島(しま)の多様(たよう)で豊(ゆた)かな環境(かんきょう)にふれ、命(いのち)のつながりを感(かん)じることができました。4面(めん)と5面(めん)に写真特集(しゃしんとくしゅう)も載(の)ってるよ!
(文(ぶん)と写真(しゃしん)・知花徳和(ちばなのりかず))

シーカヤックやシュノーケリングをした隊員。笑顔でガッツポーズ=7月30日、久米島シンリ浜
調査日程
7月28日(1日目)
森と川の固有種探し
久米島(くめじま)ホタル館周辺に生息する森の動植物と水辺の生物を調査(ちょうさ)しました。臭(にお)い、大きさ、形、感触(かんしょく)、色の五つのテーマごとに、結果を互(たが)いに発表、佐藤(さとう)文保館長から久米島(くめじま)の成り立ちを学んだほか、沼地(ぬまち)と川の生き物の違(ちが)いなどについて学びました。
7月29日(2日目)
洞窟の固有種探し
ラムサール条約(じょうやく)登録湿地(しっち)の森や白瀬(しらせ)川で、久米島(くめじま)固有の動植物を観察したほか、久米島紬(くめじまつむぎ)の里ユイマール館で伝統(でんとう)工芸を体験しました。夜は、ヤジヤーガマ洞窟探検(どうくつたんけん)。オオゲジやヒモヤスデ、オキナワコキクガシラコウモリなどの生き物を観察し、食物連鎖(れんさ)などについて理解(りかい)を深めました。
7月30日(3日目)
海の環境を知る
真謝(まじゃ)海岸の漂着(ひょうちゃく)ごみ拾いや海の生物観察を行ったほか、シンリ浜(はま)でシーカヤックとシュノーケリングを体験しました。隊員が拾ったごみは20分(ぷん)足らずで軽トラックの荷台に山積みになりました。その後、ハマサンゴが群生(ぐんせい)する岩礁(がんしょう)でサンゴの白化現象(はっかげんしょう)を観察しました。
7月31日(4日目)
島の成り立ちを知る
現地調査(げんちちょうさ)のまとめとシンポジウムで発表するテーマを絞(しぼ)り込(こ)む会議をしました。博物館見学や島の成り立ちを調査(ちょうさ)できる地質(ちしつ)・岩石スポットを見学しました。

子ども調査隊8人 地球環境考える
暖(あたた)かく雨(あめ)の多(おお)い亜熱帯気候(あねったいきこう)は、豊(ゆた)かな水資源(みずしげん)を生(う)みました。
琉球(りゅうきゅう)の島々(しまじま)の中(なか)では珍(めずら)しく、いくつもの地殻変動(ちかくへんどう)を経(へ)てきた久米島(くめじま)には、たくさんの生(い)き物(もの)がいます。
隊員(たいいん)は久米島(くめじま)の固有種探(こゆうしゅさが)しをテーマに、森(もり)や洞窟(どうくつ)、川(かわ)や海(うみ)をめぐりました。
初日(しょにち)は久米島(くめじま)ホタル館周辺(かんしゅうへん)に生息(せいそく)する森(もり)の動植物(どうしょくぶつ)と水辺(みずべ)の生物(せいぶつ)を調査(ちょうさ)しました。
におい、大(おお)きさ、形(かたち)、感触(かんしょく)、色(いろ)の五(いつ)つのテーマごとに、観察(かんさつ)を行(おこな)い、五感(かん)を使(つか)い思(おも)ったことを互(たが)いに発表(はっぴょう)しました。
安岡中学校(やすおかちゅうがっこう)1年(ねん)の長島由奈(ながしまゆうな)さんは「クロベンケイガニに興味(きょうみ)を持(も)った。巣穴(すあな)に木(き)を入(い)れるとハサミで挟(はさ)む習性(しゅうせい)が不思議(ふしぎ)」と感想(かんそう)を話(はな)しました。
国際的(こくさいてき)にも重要(じゅうよう)な湿地(しっち)であることが認(みと)められた「ラムサール条約登録湿地(じょうやくとうろくしっち)」も訪(おとず)れました。
ホタル館(かん)の佐藤文保館長(さとうふみやすかんちょう)(56)の案内(あんない)で湿地(しっち)を調査(ちょうさ)した子(こ)どもたちは昔(むかし)、島(しま)の森(もり)で木炭(もくたん)づくりや湿地(しっち)を活用(かつよう)した田植(たう)えが行(おこな)われたことを学(まな)び、人(ひと)が自然(しぜん)の中(なか)で暮(く)らしていた当時(とうじ)を想像(そうぞう)していました。
国(くに)の天然記念物(てんねんきねんぶつ)リュウキュウヤマガメを見(み)ることができた読谷中学校(よみたんちゅうがっこう)3年(ねん)の齋藤健太君(さいとうけんたくん)は「カメが岩(いわ)やコケの色(いろ)と一体化(いったいか)していて、生(い)き残(のこ)るための工夫(くふう)を感(かん)じた」と興奮(こうふん)した様子(ようす)でした。
白瀬川(しらせがわ)では、沖縄県(おきなわけん)でただ一(ひと)つの水生(すいせい)ホタルで島(しま)の固有種(こゆうしゅ)クメジマボタルの幼虫(ようちゅう)を観察(かんさつ)することができました。

川辺の生き物を観察する隊員=7月28日、久米島ホタル館周辺の川辺
伝統文化(でんとうぶんか)も環境問題(かんきょうもんだい)とつながっています。人間(にんげん)の生活(せいかつ)を良(よ)くするため山(やま)の環境(かんきょう)を破壊(はかい)すると、赤土(あかつち)が海(うみ)に流(なが)れ込(こ)み、サンゴに悪影響(あくえいきょう)を与(あた)えてしまいます。
一方(いっぽう)で、赤土(あかつち)は久米島紬(くめじまつむぎ)の染料(せんりょう)となり、パイナップルを育(そだ)てる土壌(どじょう)にもなります。
隊員(たいいん)は久米島紬(くめじまつむぎ)の里(さと)ユイマール館(かん)で織物(おりもの)づくりの説明(せつめい)を聞(き)き、実際(じっさい)に作業(さぎょう)の工程(こうてい)を体験(たいけん)しました。
安岡中学校(やすおかちゅうがっこう)1年(ねん)の名嘉山栞(なかやましおり)さんは「赤土(あかつち)が与(あた)える悪(わる)い影響(えいきょう)と良(よ)い面(めん)について考(かんが)えるきっかけとなった」と語(かた)りました。
子(こ)どもたちは最終日(さいしゅうび)、博物館見学(はくぶつかんけんがく)や島(しま)の成(な)り立(た)ちを調査(ちょうさ)できる地質(ちしつ)・岩石(がんせき)のスポットを見学(けんがく)しました。
「固有種(こゆうしゅ)」を考(かんが)えることは、それ以外(いがい)の「普通種(ふつうしゅ)」を意識(いしき)することにつながります。
水辺(みずべ)と森(もり)の動植物(どうしょくぶつ)の関(かか)わりを知(し)ることは地球環境全体(ちきゅうかんきょうぜんたい)の循環(じゅんかん)を知(し)る良(よ)い機会(きかい)となりました。
隊員(たいいん)は9月(がつ)5日(にち)、那覇市(なはし)のタイムスホールで成果(せいか)を発表(はっぴょう)します。

久米島紬のよこ糸づくりを体験する隊員。まゆをアルカリ液で煮て柔らかくし、両手で伸ばします。上手にできました=7月30日、久米島紬の里ユイマール館
自然と命 つながり学ぶ
久米島視察 歩いた泳いだ
暗いガマの中で食物連鎖(れんさ)の実態(じったい)を知り命のつながりを感じた-。「沖縄こども環境調査(かんきょうちょうさ)隊2015」の久米島視察(くめじましさつ)が7月28日から31日までありました。
「久米島(くめじま)の固有種」をテーマとした活動で、森や洞窟(どうくつ)、川そして海を観察しました。固有種を考えるためには、普通(ふつう)種やその他の自然とのつながりを考えることが重要だということに気付きました。
8人の隊員は久米島(くめじま)の自然環境(かんきょう)の中で何を感じたでしょうか。活動の様子を写真で振(ふ)り返(かえ)り、体験記を紹介(しょうかい)します。

島最大の鍾乳洞。夜の洞窟探検では暗闇にひっそりと、しっかりと生きる小さい命がいることを学んだ=ヤジヤーガマ洞窟(久米島ホタルの会提供)
ガマの食物連鎖観察
桜井久玲愛さん(港川中学校1年)
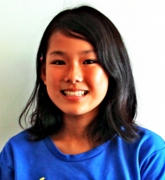
生き物と人間はつながっている。私(読谷中学校3年わたし)がそれを感じたのはヤジヤーガマ洞(どう)くつ探検(たんけん)の時だ。
コウモリのフンがあり「汚(きたな)いな」と思ったら、ミミズのようなヒモヤスデがたくさんいた。ヒモヤスデをクメカマドウマが食べる。クメカマドウマをオオゲジが食べそれをコウモリが食べる。
食物連鎖(れんさ)の様子を自分の目で観察することができた。しかし洞(どう)くつを人間が掃除(そうじ)してしまうと食物連鎖(れんさ)が崩(くず)れることを知った。
このまま人間が進化していく事により自然がこわれるかも知れない。自然を少しでも残すため水を大切に使うなど身近なところから取り組みたい。
赤土の影響を考える
當銘舞子さん(美里中学校1年)

久米島(くめじま)での調査(ちょうさ)で人と赤土の環境(かんきょう)に興味(きょうみ)を持った。赤土は海に流れてサンゴに影響(えいきょう)を与(あた)える悪い面もあるが、久米島紬(くめじまつむぎ)に利用されたりする良い面もあることに気づいた。
赤土で被害(ひがい)を受けた川や海の生き物たちのことを考え、環境(かんきょう)をどう守っていくかを伝えて行きたい。
その中でも、固有種たちは赤土の被害(ひがい)で今と昔で環境(かんきょう)は変わるのかどうかを調べていきたい。森林を伐採(ばっさい)することが赤土流出の原因(げんいん)の一つ。
例えば赤土が流れ出す森だけを切るのではなく、植林活動を行って人間にとって必要な分だけを伐採(ばっさい)する仕組みができないか調べたい。

久米島紬のたて糸づくりを挑戦する隊員。ぐるぐる、「座繰り操糸」と呼ばれる方法を体験した=7月29日、久米島紬の里ユイマール館
長い時の流れ感じた
長島由奈さん(安岡中学校1年)

時の流れと、生物の大切さを感じることができた。固有種ができるのも、何度も地殻(ちかく)変動を繰(く)り返(かえ)して、何千年という時間がかかることを知った。
その中で、どれだけの生き物が生まれ、絶滅(ぜつめつ)していったのかと考えると、地球は本当に美しいと感じる。森の中や沼(ぬま)、川では、固有種のクメジマボタル、絶滅危惧(ぜつめつきぐ)種のリュウキュウヤマガメに出会えた。
生き物は食う、食われる関係の中で、必死に次の世代へと命をつないでいる。人よりもずっと短い生涯(しょうがい)だが、それでも命の重さは人と同じぐらいだと思う。久米島(くめじま)で感じたこの考えをずっと大切にしたい。
生き物の全てに役割
儀間瑞季さん(古蔵小学校5年)

自然は全(すべ)てつながっていることを学んだ。海が汚(よご)れることで川や森や山など、他の自然にも影響(えいきょう)を及(およ)ぼすと学んだ。
固有種や天然記念物は最初から特別だったわけではなく人間による土地開発や外来種のもちこみにより生息域(いき)を奪(うば)われて数を減(へ)らした。
「固有種だから大切」ではない。その周りの生き物がいるから全(すべ)ての生き物が生きていける。虫が嫌(きら)いだから絶滅(ぜつめつ)してもいいではなく全(すべ)ての生き物がそれぞれの役割(やくわり)をもっていることを知らないといけない。
人は今ある土地を大切に利用しこれ以上自然を壊(こわ)すことの無いように工夫しなければいけない。

シュノーケリングでサンゴや海の生き物を観察する隊員。ライフジャケットをつけているので、海の底まで潜るのは大変だ=7月30日、シンリ浜の海
森に関心もつ機会に
名嘉山栞さん(安岡中学校1年)

川や海の方に関心があったが、久米島(くめじま)ホタル館のスタッフの詳(くわ)しい解説(かいせつ)を受け、木の特徴(とくちょう)や生き物の希少さを知ることができ、森に興味(きょうみ)を持つことができた。
調査(ちょうさ)隊は同じ場所へ行き、同じものを見たのに、感じたことが違(ちが)い、ミーティングの度に気付きを得る機会となった。「生き物たちのゆりかご」と表現(ひょうげん)される海の藻場(もば)が、赤土流出により光合成できなくなることを知った。
一方で、久米島紬(くめじまつむぎ)の材料や、パイナップルの栽培(さいばい)には適(てき)した土壌(どじょう)に赤土が役立っている事実も知った。赤土の悪い部分と良い部分を考える良い機会となった。
普通種に目を向けて
高村ゆず子さん(座安小学校6年)

久米島(くめじま)の固有種であるクメジマボタルの幼虫(ようちゅう)が食べるカワニナ。カワニナがいなければクメジマボタルもいなくなる。
普通(ふつう)種が固有種を支(ささ)えている。固有種を守るには周りにいる小さな生き物にも目を向けるべきだ。沼(ぬま)と川で生き物に違(ちが)いを発見できた。
沼(ぬま)にいる生き物は限(かぎ)られた場所にいて体が小さく足が細い。一方、川にいる生き物は体が大きく足もがっしりとしている。生き物は環境(かんきょう)に合わせて体を形成している。
自然は素晴(すば)らしいと感じたが同時にそのことについて理解(りかい)が進んでいない現状(げんじょう)もある。自然の素晴(すば)らしさを多くの人に伝えていきたい。

シーカヤックに挑戦する隊員。透き通る海に、心がはずむ=7月30日、シンリ浜の海
漂着ごみ海外からも
畔上英士さん(宮森小学校6年)

久米島視察(くめじましさつ)で一番印象に残ったのは真謝海岸での漂着(ひょうちゃく)ごみ清掃(せいそう)活動。
中国やマレーシアのペットボトルや漁業用の浮(う)きや発泡(はっぽう)スチロールなどが流れ着いていた。中国は500km、マレーシアはフィリピンを挟(はさ)んで2千kmも離(はな)れているが、海はつながっている。
ボトルのキャップを背負(せお)うヤドカリやごみだまりの中に天然記念物のムラサキオカヤドカリがいて、生物に影響(えいきょう)を与(あた)えている様子を観察できた。落ちているごみを拾うことや分別を徹底(てってい)するなど、身近にできることからはじめていきたい。
不法投棄の問題実感
齋藤健太さん(読谷中学校3年)

赤土などの流出問題、ごみの不法投棄(とうき)について学び、人間と自然は強くつながっていることに気付かされた。
足を進める度に赤土が舞(ま)い上(あ)がる海の藻場(もば)を観察し、悲しくなった。海岸の漂着(ひょうちゃく)ごみは清掃(せいそう)20分(ぷん)足らずでトラックいっぱいとなった。
環境破壊(かんきょうはかい)を訴(うった)えるだけではなく、その原因(げんいん)を調べ、多くの人が協力してビーチクリーンや植樹(しょくじゅ)を行えるような事に携(たずさ)わりたい。
クメジマボタルが住みやすい環境(かんきょう)を整えることで数が増(ふ)えたように、絶滅危惧(ぜつめつきぐ)種も対策(たいさく)をすれば状況(じょうきょう)はよくなると思う。久米島視察(くめじましさつ)で見たこと感じたことを伝える努力をしていきたい。

森を散策中、キノボリトカゲを発見!しっぽをつかみのぞきこむ隊員=7月29日、にぶちの森
来月5日 隊員の成果発表・シンポ
場所:那覇市・タイムスホール 入場無料
沖縄こども環境調査(かんきょうちょうさ)隊の隊員が本島や久米島視察(くめじましさつ)で学んだ成果を発表する「沖縄(おきなわ)こども環境調査(かんきょうちょうさ)隊2015シンポジウム」が9月5日午後2時から、那覇市久茂地(なはしくもじ)のタイムスホールであります。入場無料。
久米島(くめじま)ホタル館の佐藤(さとう)文保館長による基調講演(きちょうこうえん)「久米島(くめじま)の自然と生き物、こども達(たち)」があるほか、隊員8人が2人1組となり成果報告(ほうこく)を行います。
隊員全員による宣言(せんげん)、「環境(かんきょう)メッセージ」で締(し)めくくります。みなさんもこども環境調査(かんきょうちょうさ)隊員と一緒(いっしょ)に環境(かんきょう)問題を考えてみませんか!


 HOME
HOME 2011
2011