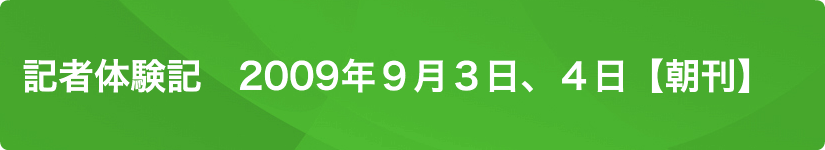2009年09月03日 【朝刊】
グアム編(上)
生態系の破壊に衝撃
子どもたちが海外の環境問題を調査する学習ツアー「沖縄こども環境調査隊」の第4陣が8月16~21日までの日程でグアムを訪れた。自然界で絶滅しているグアムクイナの飼育繁殖から、外来種のいない島への再導入の試みを調査した4人の活動を紹介する。
約60年前、米軍物資輸送とともに外来種のヘビ、ナンヨウオオガシラが島に入ってきた。ナンヨウオオガシラが、グアムクイナを捕食するため絶滅の危機に。グアム農務局は、1986年までに21羽まで減少していたグアムクイナを捕獲。飼育繁殖する取り組みをはじめ、現在は100羽余を飼育するまでになった。
沖縄のヤンバルクイナ飼育下繁殖施設は、同施設を参考に設置されている。子どもたちは「ヤンバルクイナより小さい」「餌は似ている」など類似や相違を見つけ、興味津々の様子。
調査隊はグアムクイナとの出合いに喜ぶ一方、外来種対策センターではナンヨウオオガシラがグアム島の生態系を一変させてしまった状況を知った。
「グアム島に13種類いた(在来の)鳥類が木の上を好むナンヨウオオガシラが島に入って来た後、絶滅して2種類に減ったと知って悲しくなった」と高江洲中2年の山根麻美さん(13)。
ナンヨウショウビンなど絶滅の危機にある野鳥の保護ケージでは、2羽のつがいのカラスを観察した。メスは生殖不全で繁殖することはなく、自然界に残る2羽もオスだという状況にがくぜんとした。カラスでさえ野生の個体数が激減しているのだ。
坂田小6年の外間新野(しんや)君(11)は施設の研究員が「ナンヨウオオガシラを駆除しなければならないが本当は殺したくない。ヘビにも敬意を払っている」と話したことが忘れられない。「人間が持ち込んだことでナンヨウオオガシラも迷惑だ。絶滅の道は人間から始まる」と思いを強くした。(北部支社・前森梓)
初めて出会うグアムクイナに興味津々の調査隊。(左から)外間新野くん、山根麻美さん、掘井紗らさん、宮里政吏くん=8月17日午後、グアム島・外来種対策センター
2009年09月04日 【朝刊】
グアム編(下)
身近な自然を伝える
こども環境調査隊の4人を4日間、案内したグアム農務局水生生物資源課の生物学者スーザン・メディナさん(43)は「島の人がグアムクイナについて知らないことが問題」と指摘する。
1980年代に自然界から絶滅したグアムクイナを知ってもらおうと、グアム農務局はマスコットや人間との交流に慣らされたグアムクイナを連れて学校を訪問している。
メディナさんは「若い世代は、外来種をもともと島にいた在来種と思い込んでいる。野鳥の鳴き声であふれていた本来のグアムの生態系を、人々の意識の中に残さなければ保護の機運は高まらない」と強調した。
調査3日目、一行はメディナさんらが飼育繁殖したグアムクイナ12羽をナンヨウオオガシラのいないロタ島で放鳥した。調査隊の4人は「ちゃんと結婚相手を見つけて増えてほしい」と願いを込めてグアムクイナを放った。
放鳥にはジョン・メンディオラさん(36)と息子のアブラン君(16)親子も同行。父親のジョンさんは、グアム農務局との契約で、グアムクイナを捕食するノネコ駆除を請け負っている。アブラン君は父親の仕事を通してクイナのことを周りの人々に伝えているという。「いつもはふざけあっている友達にも、僕がクイナの危機を真剣に話すから周りは分かってくれる」
国頭中3年の宮里政吏(せいじ)君(14)は、アブラン君の話が刺激になった。「何だか安心した。小学生の時は安田区のクイナの世話に参加していたけど中学に入って忙しさを言い訳にした。何かできることをしようと思う」と話した。
伊原間中1年の堀井紗らさん(12)は「外来種の持ち込みや地球温暖化など人間の身勝手な活動を考え直さないといけない。友達に話すことから始めたい」と決意した。(北部支社・前森梓)
グアム農務局のメディナさん(左)にグアムクイナの抱き方を教わりながら放鳥の準備をする調査隊=8月19日午前、ロタ島

 HOME
HOME 2011
2011